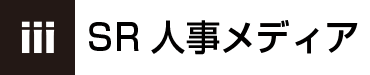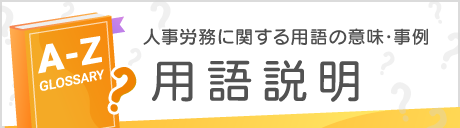テレワークと労災認定(裁判事例の増加)

在宅勤務中のけがや精神疾患が労災として認定されるケースがあると聞きましたが、どのような対応が必要ですか?
回答
■ 背景と問題点
近年、テレワーク(在宅勤務)が常態化するなか、従業員が業務中にけがをしたり、精神的負荷によりうつ病などを発症した場合に、労災認定がされるケースが増えています。
従来の「職場での事故」と違い、自宅が職場となるため、労災認定の判断がより複雑になっています。
■労災認定される主なケース
①業務中のけが(物理的な事故)
→ 例:自宅で業務に集中していた際に椅子から転倒し骨折など。
②長時間労働による過労(精神障害の発症)
→ 勤怠管理が曖昧な場合、労働時間の裏付け資料(PCログ、メール送信記録等)が鍵になります。
③業務に起因する精神的ストレス
→ 孤独感、上司とのリモートハラスメント(通称:テレハラ)などが引き金となるケースも。
■企業側の実務対応ポイント
①在宅勤務規程の整備
・労働時間、業務範囲、設備使用、災害時対応等を明確に。
・労災が起きた場合の報告フローも記載。
②勤怠管理の明確化
・打刻システム、PCログの取得、チャットツールでの出退勤報告を活用。
・「実際にどの時間に働いたか」が証明できるように。
③業務の範囲と指示系統を明示
・テレワーク中も上司の指示やタスク管理を徹底し、「私的作業」との区別をつける。
④メンタルヘルスケア
・孤立を防ぐため、定期的な1on1や相談窓口の設置。
・ストレスチェック制度の活用。
【判例①】テレワーク中の精神疾患発症 → 労災認定(東京地裁・非公開事例)
(概要)IT企業の社員が在宅勤務中、過重な業務と深夜勤務を繰り返し、うつ病を発症。
その後、自殺。会社は「在宅勤務なので管理外」と主張したが、PCログやチャ
ット履歴から業務実態が確認され、労災が認定された。
(ポイント)
・自宅勤務中でも労働時間の把握義務が会社にある。
・客観的な労働時間の記録(ログ、履歴など)がカギ。
【判例②】テレワーク中心の業務 → 過労死(さいたま地裁令和3年3月17日)
(概要)建設コンサルタント企業の男性社員が、テレワーク中心の勤務形態で月100時間
以上の残業。心疾患で急死。会社は勤務実態を正確に把握しておらず、労働時間
の管理不備が問われた。
(判決) 「会社はリモート勤務であっても労働時間の実態を把握する義務がある」とし
て、会社に損害賠償責任を認定。
【判例③】在宅勤務中の転倒事故 → 労災認定(広島労働局・2022年事例)
(概要)自宅でテレワークをしていた職員が、オンライン会議の準備中に椅子から転倒
し、肩を骨折。自宅という私的空間での事故にもかかわらず、業務中の行為と認
定され労災が認められた。
(ポイント)
・在宅勤務中であっても「業務の遂行中」であれば労災対象。
・自宅の作業環境の安全確保も、企業として指導が求められる。
■企業の実務対応ポイント
◎在宅勤務規程の整備 :労働時間、業務範囲、設備、事故時の対応など明文化。
◎勤怠管理の徹底 :打刻システム、PCログ、チャット報告などで労働時間を可視化。
◎メンタルヘルスケア :定期的な1on1面談、ストレスチェックの実施。
◎安全衛生指導 :自宅の作業環境の整備・椅子やデスクの選定についても助言。
☆☆☆参考リンク(一次情報・制度ガイド)☆☆☆
◇厚生労働省|テレワークガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
◇厚労省|精神障害の労災認定基準(令和2年改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
◇裁判所|裁判例検索システム
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
近年、テレワーク(在宅勤務)が常態化するなか、従業員が業務中にけがをしたり、精神的負荷によりうつ病などを発症した場合に、労災認定がされるケースが増えています。
従来の「職場での事故」と違い、自宅が職場となるため、労災認定の判断がより複雑になっています。
■労災認定される主なケース
①業務中のけが(物理的な事故)
→ 例:自宅で業務に集中していた際に椅子から転倒し骨折など。
②長時間労働による過労(精神障害の発症)
→ 勤怠管理が曖昧な場合、労働時間の裏付け資料(PCログ、メール送信記録等)が鍵になります。
③業務に起因する精神的ストレス
→ 孤独感、上司とのリモートハラスメント(通称:テレハラ)などが引き金となるケースも。
■企業側の実務対応ポイント
①在宅勤務規程の整備
・労働時間、業務範囲、設備使用、災害時対応等を明確に。
・労災が起きた場合の報告フローも記載。
②勤怠管理の明確化
・打刻システム、PCログの取得、チャットツールでの出退勤報告を活用。
・「実際にどの時間に働いたか」が証明できるように。
③業務の範囲と指示系統を明示
・テレワーク中も上司の指示やタスク管理を徹底し、「私的作業」との区別をつける。
④メンタルヘルスケア
・孤立を防ぐため、定期的な1on1や相談窓口の設置。
・ストレスチェック制度の活用。
【判例①】テレワーク中の精神疾患発症 → 労災認定(東京地裁・非公開事例)
(概要)IT企業の社員が在宅勤務中、過重な業務と深夜勤務を繰り返し、うつ病を発症。
その後、自殺。会社は「在宅勤務なので管理外」と主張したが、PCログやチャ
ット履歴から業務実態が確認され、労災が認定された。
(ポイント)
・自宅勤務中でも労働時間の把握義務が会社にある。
・客観的な労働時間の記録(ログ、履歴など)がカギ。
【判例②】テレワーク中心の業務 → 過労死(さいたま地裁令和3年3月17日)
(概要)建設コンサルタント企業の男性社員が、テレワーク中心の勤務形態で月100時間
以上の残業。心疾患で急死。会社は勤務実態を正確に把握しておらず、労働時間
の管理不備が問われた。
(判決) 「会社はリモート勤務であっても労働時間の実態を把握する義務がある」とし
て、会社に損害賠償責任を認定。
【判例③】在宅勤務中の転倒事故 → 労災認定(広島労働局・2022年事例)
(概要)自宅でテレワークをしていた職員が、オンライン会議の準備中に椅子から転倒
し、肩を骨折。自宅という私的空間での事故にもかかわらず、業務中の行為と認
定され労災が認められた。
(ポイント)
・在宅勤務中であっても「業務の遂行中」であれば労災対象。
・自宅の作業環境の安全確保も、企業として指導が求められる。
■企業の実務対応ポイント
◎在宅勤務規程の整備 :労働時間、業務範囲、設備、事故時の対応など明文化。
◎勤怠管理の徹底 :打刻システム、PCログ、チャット報告などで労働時間を可視化。
◎メンタルヘルスケア :定期的な1on1面談、ストレスチェックの実施。
◎安全衛生指導 :自宅の作業環境の整備・椅子やデスクの選定についても助言。
☆☆☆参考リンク(一次情報・制度ガイド)☆☆☆
◇厚生労働省|テレワークガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
◇厚労省|精神障害の労災認定基準(令和2年改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
◇裁判所|裁判例検索システム
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
The following two tabs change content below.


人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 目標達成に取り組む仕組みづくり
- NEXT
- 育児休業復職後の賃金について